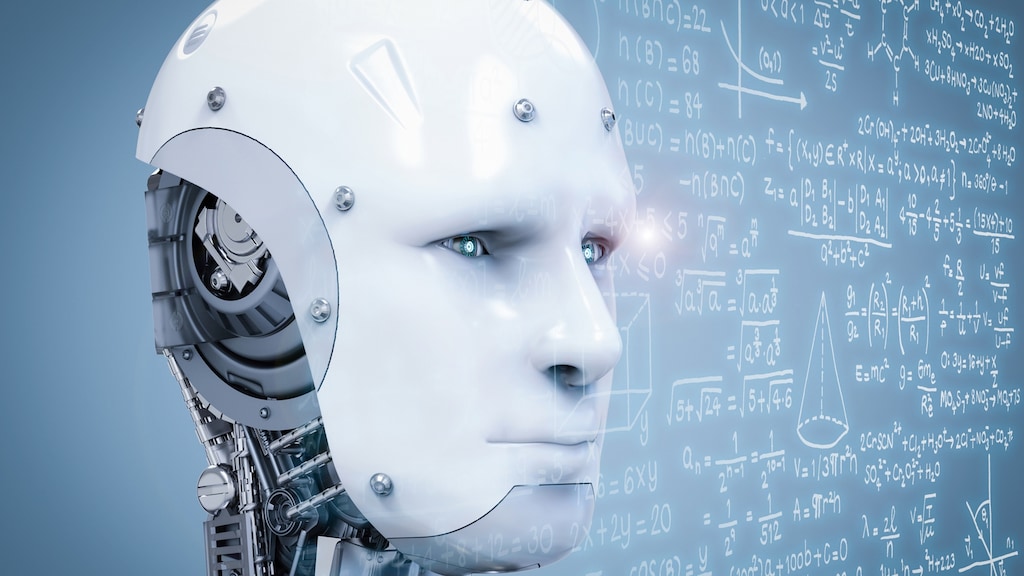【目次】
不気味の谷現象(uncanny valley)とは?
不気味の谷を感じる原因とは?理由を探る検証実験例
不気味の谷のまとめ
不気味の谷現象(uncanny valley)とは?
不気味の谷現象(uncanny valley)とは、1970年にロボット工学者で東京工業大学の教授(当時)の森政弘氏により提唱された概念です。エッソ・スタンダード石油の広報誌「Energy(エナジー)」第7巻第4号でエッセイ「不気味の谷」を発表しました。エッセイ「不気味の谷」の全文は、「GetRobo(外部サイトに移動します)」に再掲されています(2025年2月現在)。2005年に米インディアナ大学情報科学のロボット工学者カール・マクドーマン氏らにより英訳が紹介されたことで、「不気味の谷」が世界的に注目を集めました。
不気味の谷現象は、ヒューマノイドとも呼ばれる人型ロボットなど、人間のような姿や性質をもつロボットに対して、あまりに人間に近づきすぎている場合に不気味さを感じる心理的な反応を指します。人々は、人間のような性質をもつロボットに親和感を抱きますが、人間との類似性が高くなると急激に親和感が下がり、不気味さ恐怖を感じる地点があります。人間との類似度をx軸、ロボットに対する親和感をÝ軸とした場合、ある時点でグラフが谷底に落ちるように急激に下がることから、この心理的な現象は、「不気味の“谷”」と呼ばれています。なお、類似度がさらに上がり、人間との区別がつかないほどになると、再び好感をもつようになることも発表されています。
2012年には、アメリカの電気工学技術の学会誌「IEEE Spectrum」にインタビュー記事「An Uncanny Mind: Masahiro Mori on the Uncanny Valley and Beyond(外部サイトに移動します)」が掲載されました。当インタビューで森氏は「不気味の谷は、もともと蝋人形や電動義手に感じていた不気味さをロボット全般において考えるうえで生まれた、個人的経験に基づいた説」だと述べています。当時よりもロボットやAIが身近になった現在、不気味の谷現象はあらためて注目を集めています。
関連記事:シンギュラリティはいつ起こる?意味やAIによる影響、2045年問題を解説
不気味の谷を感じる原因とは?理由を探る検証実験例

不気味の谷を感じる理由や心理学的根拠はまだはっきりとわかっていませんが、不気味の谷現象が起こる原因を探る研究は世界各地で行われています。いくつかの例を紹介します。
脳波パターンとの連動
ケンブリッジ大学とドイツのアーヘン工科大学は、2019年に学術誌「Journal of Neuroscience」で「Neural Mechanisms for Accepting and Rejecting Artificial Social Partners in the Uncanny Valley(外部サイトに移動します)」を発表しました。
不気味の谷における人工社会的パートナーの受け入れと拒否の神経メカニズムについての研究です。20名ほどの被験者に「人間」「ロボット」「ハイブリッド」の複数の種類に分けた写真を見せて脳波をMRI測定し、嫌悪感と親近感の脳波パターンを調査したところ、社会的評価の処理にかかわる腹内側前頭前皮質(VMPFC)の脳波パターンと不気味の谷現象の活動パターンが一致したことから、脳波パターンが不気味の谷現象と連動していることが確認されました。加えて、実験結果から、不気味の谷現象の反応には個人差があることも明らかになっています。
全体処理(configural processing)
米インディアナ大学情報科学のロボット工学者カール・マクドーマン氏と、認知心理学者のアレックス・ディール氏は、2021年に学術雑誌「Journal of Vision」で「Creepy cats and strange high houses: Support for configural processing in testing predictions of nine uncanny valley theories(外部サイトに移動します)」を発表しました。
不気味の谷現象は、目鼻などの顔のパーツの大きさや位置に対する感受性によって引き起こされるとする全体処理(configural processing)説が最も支持されるとしていますが、末尾では、「今後の研究では、不気味の谷の原因とメカニズムを説明するために、理論をさらに詳しく調査する必要がある」とまだ研究が必要であることを示しています。
人間とアンドロイドの交流実験
アダム・ミツキェヴィチ大学(ポーランド)のダビド・ラタイチク氏は、2023年に学術誌「International Journal of Human–Computer Interaction」で「The Importance of Beliefs in Human Nature Uniqueness for Uncanny Valley in Virtual Reality and On-Screen(外部サイトに移動します)」を発表し、不気味の谷現象を引き起こす要因として、人間特有の能力だという確信が揺るがされることが大きいことを示していると指摘しています。
仮想カフェ内(VR)で参加者とロボット型、やや人間に似ているロボット型、中程度人間に似ているロボット型、人間型の4タイプのアンドロイドが対峙し交流するという実験を実施したところ、人間型よりロボット型の方が不気味と感じる、中でも、もっとも不気味と感じるのは人間に中程度似ているロボット型という結果となりました。参加者は画面上のシミュレーションでもVR同様の実験に参加しましたが、結果は同じでした。これらの実験結果を、不気味の谷現象について事前知識を持つグループと持たないグループとで比較しても、事前知識の有無による差は見られませんでした。
AIを活用した検証実験
日本国内にも興味深い研究例があります。国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)は2023年5月に「心理学の手法をAIに応用し「不気味の谷」現象を検証(外部サイトに移動します)」を発表しました。この研究は、画像に対する「不気味の谷現象」のような感情評価を、AIを使うことで実験し明らかにした点が画期的だといえ、不気味の谷現象の研究で、AIを使った世界初の研究とされています。
使用されたAI技術はCLIPと呼ばれる最新の技術です。AIには画像と画像を見た人間が作成する説明文の対応関係、つまり「人間が画像の内容を言語として表現する傾向」を学習させます。そして、このAIに用意した画像を入力して、一致するのはどのような単語(特に感情表現に関する単語)かを調べることで「人間が画像の内容をどのような感情語で解釈するか」が調査されました。AIが活用されたことで、リアルな環境で実験する場合とは比較にならないほど膨大な数の画像について、感情語の対応傾向が調べられました。
これらの調査の結果、画像に対する不気味の谷現象のような感情語表現が、AIでも再現できることが確認されました。この技術は、アバターやロボットのデザインを評価する際に、AIを活用できる可能性があるということを示しています。今後、より人間の脳の情報処理に近いAIが開発されれば、さらに人間に近い感性評価が自動的に再現できる可能性があり、人間に優しい対話型ロボットなどの実現に生かせると期待されています。
不気味の谷現象のまとめ
不気味の谷現象についての要点を、以下にまとめます。
・不気味の谷現象(uncanny valley)とは、1970年に日本のロボット工学者である森政弘氏が提唱した概念で、人型ロボットなどがあまりにも人間に近づきすぎている場合に不気味さを感じる、心理的な反応を指す。
・ロボットやAIが身近になった現在、不気味の谷現象(uncanny valley)はあらためて注目を集めている。
・不気味の谷現象(uncanny valley)が起きる理由や心理学的根拠はまだはっきりとわかっていないが、原因を探る研究は世界各地で行われている。
(免責事項) 当社(当社の関連会社を含みます)は、本サイトの内容に関し、いかなる保証もするものではありません。 本サイトの情報は一般的な情報提供のみを目的としており、当社(当社の関連会社を含みます)による法的または財務的な助言を目的としたものではありません。 実際のご判断・手続きにあたっては、本サイトの情報のみに依拠せず、ご自身の適切な専門家にご自分の状況に合わせて具体的な助言を受けてください。